34歳、国立大卒の美しき才女、高木帆希(たかぎ・ほまれ)。
父親は作家の傍らコメンテーターとしても人気の有名人で、「家事手伝い」という名の「無業」で10年もの間、ぬくぬくと過ごしてきた帆希。
そんな働かずとも裕福に暮らしてきた彼女に、突如、不幸な出来事が降りかかる。
再び「社会」と向き合わざるを得なくなった無業の女は、どのようにサバイブするのか?
「おはようございます、高木様。いつものでよろしいでしょうか?」
「ええ。先にスパークリングを頂くわ」
「かしこまりました」と上品に微笑む顔なじみのウエイター。
いつもと変わらない朝が、今日も始まろうとしている。
目白にある私の家からほど近い、ホテル椿山荘にある『イル・テアトロ』。
ここのプレミアムブレックファーストを頂くのが、私の日課だ。
甘みのあるハニーハムと、ザバイオーネソースの酸味が絶妙なエッグズベネディクトに、薫り高い黒トリュフがスライスされ、食欲をそそる。キリっとしたシャンパンを流し込むとシナプスがパチパチとつながっていくようだ。
私は週三回、ここ『イル・テアトロ』で朝食をとる生活をしている。
ーもう10年か…。
私は、高木帆希。34歳、独身。横浜にある国立大学の修士課程を卒業した私は、家事手伝いとして父の仕事をささやかにサポートしている。
父は、恋愛小説を得意とした作家で、映像化はもちろんのこと、最近では港区にあるテレビ局のお昼のワイドショーのコメンテーターとして人気を博している。
ロマンスグレーの髪に、ちょっとレトロな黒ぶち眼鏡をかけた父を、私は生真面目で遊びのない人だなと思っているのだが、世間では、「知的でセクシー」という評判らしい。不思議なものだ。
あんなにも男と女の濃密な情事を鮮烈に描く父だが、この10年ずっとそばにいても、女の影を感じたことは一度もない。
ーお母さんのこと、今でも愛してるのかしら…。
母は私が大学院に通っていた頃、乳がんを患い他界した。社会人だった兄は、すでに独立していたこともあり、私が母の代わりとして父の面倒を見ているというわけだ。
「高木様、おさげしてもよろしいでしょうか?」
「ええ、ご馳走様。今日も美味しかったわ」
そう言って私は、心からの感謝を伝えると、小さな泡が弾けるグラスをクッと飲み干した。遅めの朝食を優雅にホテルのレストランで頂ける生活に、私は満足している。
ゆったりと流れる幸福な時間は、これから先“私が望む限り”続くものだと、この時の私は信じて疑わなかったー。



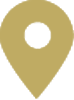


































この記事へのコメント
説教して娘に嫌われるのが嫌だったのかもしれないけど、いきなり放り出すのは無責任。
散々甘い顔をしてきた父親にも問題があると思う。