週末明けの月曜日。表参道のオフィスには、毎朝10時に出社する。
「おはよう」
私は親友の園子と、PR会社を経営しているのだ。メンバーは計5人。私と園子のほかは契約社員で雇っている20代の女子が3人の、小さな会社である。
「おはよう聖良。今日の展示会のサポートは私が行くから、溜まっていた企画書仕上げちゃっていいよ。来週、提案だからね」
私の少し前に出勤した園子は、マックスマーラのテディベアコートをハンガーにかけながら、私のほうを振り返った。
「助かる!よろしくね」
園子はスケジューリングや資金繰りなどを段取るのが絶妙にうまい。
一方、私は交渉能力に長けている。お互いのないところを補い、これまでうまくやってきた。
園子は大学の時からの友達。8年前に転職した会社で、偶然再会したのだ。
再会を喜び、会社帰りに飲みながら話をしていると、園子も現状の給与に満足していないことを知った。
「2人で会社立ち上げたら、ひょっとして結構稼げるんじゃない?」
私が発した、この一言から始まったのが、今の会社だ。
立ち上げ当時と会社の規模は変わらずとも、クライアントをきめ細かくサポートし、毎年業績を伸ばしている。クライアントの多くはアパレルメーカーで、表参道にオフィスを構えたのが3年前。クライアントとの距離を縮め、1社からより多くの利益を得られるようにしようという園子の考えからだった。
「あのね、聖良。展示会は18時30分アップだから、今日仕事上がったら、ちょっといい?」
向かい合わせに座っている園子が、画面越しに私を覗く。
「あー、今夜は約束が…と思ったけど、大丈夫。リスケするから」
園子とはたまに、会社帰りに食事をしながら未来の展望について話し合う。実は、2週間ぶりに彼と会う約束をしていたが、私は躊躇なくリスケすることにした。
『ごめん、今夜会食が入っちゃった。別の日に変えてもらってもいい?』
恋人にしてはやりとりが少ないLINEのトーク画面に、メッセージを入力する。
送信と同時に既読になり、『わかった、おつかれ』と短い返信があった。
― 慎之介、ごめん!
3つ年下の慎之介とは付き合って2年になるけれど、特別に燃え上がった記憶もなく、なんとなくゆるゆると今日まで続いているような関係だ。
彼はウェブマガジンの編集者で、撮影や取材以外の仕事はほぼリモート。仕事自体は忙しく、休日返上で働いていることは知っているが、自宅作業なのでたいがい私の都合に合わせてくれる。
彼のことを、好きだとは思う。
LINEのやりとりは毎日というわけじゃないがちょくちょく送るし、月に2、3回会って食事をし、どちらかの家に泊まる。
会えば安心できるし、居心地は悪くない。
だけど「このままでいいのかな」とも思っている自分がいるのも事実。2人の間で結婚の話は出たことがないし、私もさほど結婚に興味がない。ただ、この先、どうやって歳をとっていくのか、時々考えるようになった。
私の人生に園子は絶対に必要だけど、慎之介は…。
親友と恋人を天秤にかけるなんて、よくないことだとわかっているけれど、どうしてもそう考えてしまう私がいた。
◆
仕事が終わり、19時に代々木八幡の『ヨヨナム』で園子と落ち合う。園子は10分ほど遅れてやってきた。
「ごめん!私から誘ったのに遅れちゃった。タクシー捕まらなくて、電車で来たの」
園子みたいに柔らかく笑う女を私は知らない。大変なことも顔には決して出さず、困難にぶち当たっても最後まできっちりやりきる強さもある。
園子と組んで良かったと、私は常日頃から思っている。
― きっと、園子もそう思っているはず…。
グラスに注がれたシンハービールの泡を1口、2口と美味しそうにすすると、園子は言った。
「聖良、あのね。今日は大事な話があるの」
こんな前置きをするなんて、園子にしては珍しい。そう思った矢先、信じられないことを彼女は打ち明けたのだ。
「私、会社辞めようと思ってる」





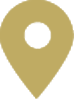


































この記事へのコメント
って言われてるのに聞かずに、いなくなったら会社続けられないって説得に入っちゃうところがだめだよね。
よっぽど聖良とやっていけない理由が園子にあるとか?