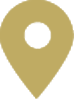旬の素材を引き立てるという共通点を持つROKUと和食。さて、相性はいかに?
野崎氏の語りかけをきっかけに、ボトルに視線を向けたふたり。
その特長的なデザインにも惹かれたようだ。
“六”という墨文字は荻野丹雪氏によるもの。また、ラベルが越前和紙というのも和を静かに表現していて、情緒を感じる。
繊細さと華やかさ、どちらをも併せ持つデザインは、『分とく山』の空間とも違和感なく溶け込む。
「今日のお料理との相性もとても良いので、飲んでみますか?」
そのひと言にふたりはさらに目を輝かせ、うなずいた。
ROKUジンソーダとともに、1皿目に供されたのは「水蛸のあらい」。
涼しげなガラス皿に敷かれた蓮の葉の上に盛られた水蛸が、まるで花のように存在感を放つ。蓮の花に見立てたその様からは、四季を感じることができた。
「わさびを溶いた梅醤油で召し上がっていただき、その後にROKUジンソーダを飲んでみてください」
促されるまま試してみると…、梅の酸味とわさびの香りに「ROKU」の爽やかな味わいが呼応した。
「スッキリとした味わいと喉越しに、暑さが吹き飛びますね」。
そう言って、彼女は驚きの表情を見せた。
続く「鰻の葉月あえ」は、揚げたヤングコーンやごぼうチップスの食感が愉しいひと皿。
北海道産の青海苔の磯の香りと、貝殻の器に見立てた生春巻きの透明感のある皮が海を彷彿とさせる。
「鰻の滋味深い味わいと一緒に柚子の香りが抜けるのが印象的!とても爽やかで、ROKUジンソーダともすごく合いますね」
そう彼が感想を漏らすと、「『ROKU』には鰻との相性が良い山椒も使われていますが、柚子も含まれているんです。そこで、『ROKU』と料理で柚子の味わいや香りをリンクして愉しめるよう調理してみました」と、いたずらっ子のように野崎氏が微笑んだ。
この日の焼き物は「夏鴨の酢煮」。
「店では通称“UFO”と呼んでいる」と笑う器に盛られたのは、ピンクの断面が美しい鴨肉。
肉の後ろには生姜、ミョウガ、カイワレ、ネギ、大葉という5種類の薬味を忍ばせ、ゼリー状の酢とともに味わうという趣向だ。
ねっとり舌に絡みつく鴨肉の旨みに薬味が絡み合い、夏らしい清涼感が口内を満たす。
「お料理を味わった後にROKUジンソーダを飲むと、すごく口の中が爽やかになって、暑さで落ちた食欲が戻ってくるのを実感します」
そう彼女が話すと、野崎氏は優しい眼差しを向けてこう話した。
「『ROKU』自体を薬味ととらえて、料理をつくってみたら面白いんじゃないか?そう考えて生まれたのが、今日の料理です。ジンには苦味のイメージがありますが、薬味もそれぞれで食べたら苦いでしょ。でも合わせるとハーモニーに変わる。まさに『ROKU』と同じですよね」
相乗効果で引き立て合う和食店とROKU。その根底には職人の技や工夫があった。
和食とジャパニーズクラフトジン ROKU(六)。
四季の素材を使い、伝統を継承しながらも、常に客を魅了し続ける理由。
“本質を追求すること”、そして“時代の空気感をとらえ、変化していくこと”。
この2つのバランス感覚こそ、一流の和食店とROKUの共通点なのかもしれない。