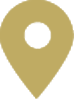和食の名店ひしめく東京だが、職人の腕と東京らしい艶やかさが揃う店となるとそう多くはない。
洒落た立地となればさらに限定されるが、すべての条件を満たす店が表参道にある。
洗練された和の設えの中、日本の美学を体感できる名店に、本気のデートで足を運びたい。
◆
※コロナ禍の状況につき、来店の際には店舗へお問い合わせください。
南青山の行き止まりには、本物を知る者だけが集う場所がある
表参道駅から徒歩5分。高級低層マンションに囲まれた一角に『宮坂』は居をかまえる。
南青山らしいスタイリッシュなエリアのど真ん中だが、店内に入れば一転、そこは背筋が伸びるようなしっとりした空間だ。
廊下に設えられた床の間には季節ごとの御軸がかけられ、カウンターの前は蹲のある中庭。
窓の京すだれも漆喰の壁も美しく、本物の和の内装は夜になれば艶やかさを放つと、ふたりに実感させる。
この席に着いた瞬間から、ふたりの経験値がまたひとつ上がる
カウンターに立つのは、京都にある日本料理の名店で腕を磨いた宮坂展央さん。
「せっかくの非日常はリラックスして楽しむことが大事。日本再発見のつもりで、分からないことや興味を持った物についてはなんでも聞いてほしい」と話す。
宮坂さんは器の目利きでもあり、希少で背景を連想させる銘品が多くそろう。
伊勢海老がのる魯山人の割山椒の器が好例だ。山椒は10〜11月に実がはじけるため、その時期にだけ出す器で、手にとって眺めると割れ方が実にリアルである。
日本料理のなんたるかを大切な相手と体感し、ふたりで経験値を高めたい
【一品目】先付
日本料理における前菜の位置付け。後に続いていくおかずの前に出されるので、先付と呼ばれるようになった。
菊花あんをかけた真名鰹と大黒しめじ、舞茸。器は魯山人の、志野菊文蓋付碗。
このひと品と器の組み合わせのように、器をヒントにして料理を決めることも多いのだという。
【二品目】造里
その日のとっておきの鮮魚を処理して、切り身で提供する料理。お皿の上にツマや魚で“里”を造るという意図が語源。
常に白身とまぐろの組み合わせで、この日の白身はヒラメ。まぐろは「やま幸」からで、青森の延縄漁によるもの。
器は、京都の古美術屋で購入した古染付(明の時代に作られた染付磁器)。
【三品目】煮物椀
折敷にのせて提供する、深めの椀に盛り付けた汁のこと。すまし仕立ての汁で、季節の食材が具として使われる。
さっと火を通した鱧と松茸にお出汁を注いだお椀。ふたつの旨みや香りが、お出汁に品よくにじむ逸品だ。
器は古い輪島塗で、蓋には見応えある稲穂とすずめの蒔絵が施されている。
【四品目】焼物
食材に直火または間接的に火をあてて焼く料理。調味はさまざまで、基本的には季節の魚が使われる。
のどぐろの幽庵焼き。のどぐろ独自の脂を繊細なものに感じられる火入れが秀逸だ。
こちらの器も古染付。茶事の時にしか使われてこなかったので、絵柄も美しいまま残っている。