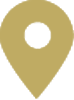ROKUと小山氏の料理をつなぐ「つくり手」の想い。それぞれの職人が込めた想いとは?
世界に日本料理を発信してきた小山氏も認めるROKU。数年前に行われた世界の有名シェフとともに参加した日仏のイベントでは、ROKUのブースが大盛況だったのを目の当たりにしたという。
「今日はROKUがより美味しいと思える料理を用意しましたよ」
そう言って、小山氏は包丁を取り出した。
「でもその前に、まずは飲んでみてください」
そう小山氏に促され、初めて口に含んだ2人。
「すごく華やかな香りなんだけれども、濃厚というよりは柔らかで控えめな感じに繊細さを感じます」
そう彼女が呟く。
続けて彼は…
「ジンの強いイメージを軽やかに覆された感じ。すごく飲みやすくて驚いた」と感想を漏らした。
「つくり手の強いこだわりを感じますよね。実際、ROKUで使用している6種の和素材は丸1年かけて、それぞれの旬の時期に手摘みで収穫していると聞けば、納得です。僕たち料理人が大切にしているのも四季や旬。だから和食に合わないはずがない」と、小山氏も太鼓判を押す。
ROKUは旬をとても大切にしているお酒だ。日本に古来よりある「すべての季節に命が宿っている」という考えに沿い、季節の廻りをを大切にし、移り変わる節(時)に心躍らせ、その旬という瞬間の刹那を愉しむ。
一本のお酒にこれだけのドラマが隠されているとは、興味深い。
1品目は「タコのカーボン仕立て」。
小山氏自ら監修したというカーボングラファイト製の釜で、じっくりと柚子とともに炊いたタコは、木の芽のペーストとともにいただく。
「あえて甘さを控えめに炊いているのは、ROKUの甘みをより引き出すため。木の芽は山椒と呼応し、一緒に炊いた柚子がほのかに香る。ROKUのおいしさを感じられるように、仕掛けているんです。ゲストひとりひとりに合った料理を出すのは料理人の当然の仕事。だからうちの料理は月替りでなく、“その時替わり”のおまかせ料理です。今日はROKUを主役に見立て、お客様に満足いただけるよう、お料理を構成しました」
そう言って茶目っ気たっぷりの表情を見せた小山氏。このタコは、その言葉をまさに証明する1品だ。
「おっしゃる通りですね。最初はスッキリと感じていたROKUの味わいに、甘さを感じるようになりました。和食とジンって合うのかな?と思っていたんですが、このROKUジンソーダはとても合いますね。心がほぐれていくのを感じます」と彼女も絶賛。
ROKUがもたらす香りや味わいは、四季を通じた旬の和素材の調和であると同時に、移りゆく季節・自然に関わりを持ってきた日本ならではの繊細な心、感性をも感じさせるようだ。
続いて供されたのは、“鯛といえば『青柳』”と言わしめる、小山氏の名声を築いたと言える1皿だ。
鳴門から届いた今朝締めたばかりという鯛に、2人の眼前で包丁を入れていく。
背骨の丸みが残るように一太刀で刃を入れるその作業に、迷いは一切ない。
「おろすところから刺身は始まっている」と氏の言葉通り、口に入れれば弾力のある食感、確かな甘みが広がっていく。
「噛むほどに旨味もふくらんで、鯛ってこんなに力強い魚だったとは!ROKUが余韻をさらに後押しして、幸福感で胸がいっぱい。1年を締めくくるディナーに、ふさわしいですね」と彼も満足そうな表情を浮かべた。
確固たるアイデンティティを持つ両者だからできる“我を殺す”ということ
最後に「料理人としての哲学は?」と2人に尋ねられた小山氏は、こう語った。
「我をいかに殺して、素材の魅力を引き出すか。その人を喜ばせられるか。それが料理だと僕は思っています。と同時に、アイデンティティのない人間は尊敬されない、というのも世界を見てきた実感です。だから生涯、日本人として日本料理を追求していきたいですね」
時に料理の引き立て役に回りながらも、自身も素材の魅力に富んだジャパニーズクラフトジンとして、確かなアイデンティティを持つROKU。
稀代の料理人とROKUの共通点がそこにはあった。