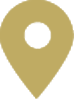ホカホカのおにぎりやお稲荷さんが、無性に沁みるときがある。
美味しいお米を食べると、疲れも吹っ飛び、ホッとした気持ちになれるのはなぜだろうか…
今回は、シンプルな具のおにぎりから豪華食材を楽しめる逸品まで、幅広くご紹介。
日本のお米の美味しさを再認識できる絶品ご飯を堪能あれ!
1.美味しさの基本を作る、米・海苔・塩に妥協なし!『ぼんご』
1960年創業の老舗おにぎり専門店『ぼんご』。開店から閉店までの間、ひっきりなしにお客が訪れ、皆それぞれ好みのおにぎりを楽しんでいる。
『ぼんご』のおにぎりは、注文を受けてから作る、にぎりたての寿司屋スタイル。
ホカホカの炊きたてご飯を手際よく握り、「お待たせしました~」と元気な声でお客に手渡す。
『ぼんご』のおにぎりは、ホッカホカぶり、おにぎりを頬張った時の具の多さ、ふっくらとした食べ心地が特徴。
初めて食べる人は、合計3度驚かされることになるのだ!
この熱々&ふっくらとした食べ心地を生んでいるのが、ぼんご特有のおにぎりの作り方だ。
通常、おにぎりと言えば当然握るものと考えるだろう。しかし、熱々の炊きたてご飯を握ることは到底できない。
そう、同店では、海苔でお米と具を“包みこんでいる”のだ。
言わば、海苔は器の役割。お米一粒一粒を口の中で感じられるように包む加減が絶妙で、職人技が光るポイントなのである。
1個約250gと大きなおにぎりだが、2個はあっという間に完食できてしまう。
3個目も行けるかも…と思えてしまうほど、ふっくら食感なのだ!
「ぼんご」の人気の秘訣のひとつともいえる、55種も揃う具にも注目してほしい。
女将・右近さんは「品切れゼロ」をモットーに、全ての具材が開店から閉店まで絶えることがないのも嬉しい心遣い。
そんな女将のポリシーにより、55種という膨大な量の具から、好きなものを選べるのだ!
『ぼんご』ファンをさらに幸せな悩みへと導いているのが「トッピング」だ。これは、好きな具を2種ほど組み合わせオーダーすることができるシステム。
55種でも制覇するのは一苦労なのに、この「トッピング」によって、具の種類はほぼ無限に広がっているといっても過言ではない。
例えば、「すじこ」と「さけ」の二大人気具材を組み合わせた、超贅沢なおにぎりだって叶ってしまうのである。
もちろん、お米や素材へのこだわりも並々ならぬものがある。
お米は、おにぎりに適した粒の大きさである、新潟県岩船産コシヒカリの棚田米。器となる海苔は、味と香り、そして歯切れの良い有明産の海苔。
そして塩は、ミネラル豊富でクセのない沖縄の塩に、胡麻をブレンドして使用している。
常におにぎりとのマッチングを考え、お米を引き立ててくれる素材を探し続けた同店が辿り付いた、究極のカタチなのだ。
「究極のおにぎり」、是非食べに行ってほしい!
2.職人技が光る!ふんわりおにぎりの秘訣『宿六』
創業は昭和29年。白いご飯はまだ高級品だった頃、子どもから大人までおいしいお米を食べて欲しいという先代の想いから誕生した『宿六』。
店内でにぎりたてを味わうのもおすすめだが、1個からテイクアウトもできるので、ピクニックのお弁当としても最適だ。
プロのおにぎりの握り方とは、いったいどんなものなのか? 三代目・三浦洋介氏に、その技を見せていただいた。
木枠に炊きたてのご飯を優しくはめ込み、中央に穴を開け、そこに具を入れていく。具は、ご飯からはみ出そうなほど豪快に入れられる。
塩をひとつまみ手に取り、木枠からご飯を取り出して握る工程へ。
ふんわりとした食感に仕上げるため、握りすぎないようにしていると三浦氏。
ごはんで具を包み込むように数回軽く握るのみなのに、形良く仕上がっていく様子はまさに職人技だ!
カウンターのガラスケースに並べられたおいしそうな具の数々を眺めつつオーダーできるのも、創業当時から変わらないスタイル。
約20種類の具は、全て食べたくなるほど魅力的なものばかり!
人気ナンバーワンは「さけ」。定番・紅鮭を使用しないのが宿六スタイルで、若い個体で身にたっぷりと脂&栄養がつまった、時鮭を使用している。
おにぎりを作る上で欠かせないのが「米」と「海苔」。
米は、年ごとに色々なものを食べ比べ、ご主人自身がおいしいと思ったものを仕入れる。そして海苔は、磯の香りの強さとパリッとした歯ごたえが特徴の江戸前海苔を使用。
そのまま塩結びで食べてもおいしいと感じるこだわりの食材に、具のおいしさが加わるのだから間違いないのだ。
一度は足を運んで、絶品おにぎりを口いっぱいに頬張りたい!