樹里(じゅり)との出会い
鴨川を走る風が、喧騒を風情に変えて通り過ぎた。
仕事終わりで訪れた『ヴィネリア ティ・ヴィ・ビー』の川床。
川沿いに灯るあかりに照らされ、ちらほらと目に入る夏着物姿の女性。そのしっとりとした艶やかさに、紀夫は思わず目を細めた。
京都の夏が、いよいよ始まろうとしている。
「ちょっと紀夫、聞いてる?」
ふいに声をかけられ顔を上げると、会社同期(紀夫は日本を代表するゲーム会社の京都本社で勤務している)の夏子が、大きな目をくりくりさせて紀夫を覗き込んでいた。
「あ…ごめん、ぼーっとしてたわ」
「まあ、紀夫がぼーっとしてるのはいつものことやけど」
そう言ってからかう夏子の隣で、くすくすと品の良い笑い声がする。
萬田樹里(まんだ・じゅり)。つい先ほど、彼女は囀るようにそう名乗った。
夏子の、同志社大時代からの友人だという樹里は同じ29歳のはずだが、眉下でカットされた前髪にセミロングのストレートヘア、そして加工の跡をまるで感じさせないナチュラルなメイクのせいで随分と若く見えた。
気がつけばあっという間に日没を迎え、暗闇に沈んだ川床はぐっと大人な雰囲気を醸している。
気づかれぬよう、そっと樹里の様子を伺う紀夫は、ライトに照らされた彼女の横顔を見つめてハッと息を飲んだ。
さっき正面から見たときには気づかなかったが、彼女は思いがけず彫りの深い、大人びた横顔をしている。
咄嗟に目を逸らすのが遅れ、こちらに気づいた彼女と目が合う。
恥ずかしそうに小さくはにかむ彼女の仕草を、紀夫は「愛らしい」と思った。
そのギャップが、紀夫の心を震わせたのだ。
とはいえそれは、一目惚れとか、ビビッときたとか、そんな大げさな感情ではなかった。
しかし漫画やドラマと違う三次元の恋は、えてしてそんな些細なことから始まるものだろう。
「なあ、一人ずつ好みのタイプを言っていかへん?」
ノリノリでそんな提案をしてきたのは、紀夫の立命館大学時代からの友人、二木龍之介(にき・りゅうのすけ)だ。
卒業してからもひと月と空けずに会っている彼は親友と呼べるはずだが、しかし性格はというと紀夫とは真逆である。
学生時代から上昇志向の強かった龍之介は、大学卒業後そのままロースクールに進学。
幾度かの挫折を経てようやく法曹界への切符を手にし、現在は烏丸二条にある法律事務所で弁護士としてのキャリアを積んでいる。
しかし永年にわたる勉強漬けの日々は、彼の恋愛観を大いにこじらせたらしい。
今宵の集まりも、暇さえあれば食事会に精を出している龍之介から「誰か女の子誘ってきてよ」と無茶ぶりされ、同期の夏子に頼んでセッティングしてもらった経緯がある。
「それじゃ…まず俺から。名前は、二木龍之介。弁護士やってます。好みのタイプは、田中みな実!」
ドヤ顔で言い切る龍之介に「お前、ブレへんなぁ」と紀夫が半ば呆れた声を出すと、夏子も「…いるよなぁ、あざとい系に嵌る男」と冷ややかに応えた。
しかしそんな時も樹里はというと、夏子の隣で静かに微笑を浮かべるだけだ。
どこか浮世離れして見える彼女は、ほとんど自分から話さない。
その立ち居振る舞いは、まるでこういう場に来ること自体が初めてかのような不慣れさを感じるほど。
…29歳という年齢で、まさかそんなことはあるまいが。





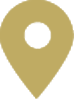

































この記事へのコメント
…まさか任〇堂?