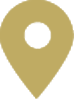本来の江戸前の仕事こそ魚の個性を引き出す技
四谷『すし匠』中澤圭二氏の鮨ネタには、すべて「エイジング」と頭に付けて読み替えていただきたい。冗談ではなく、熟成こそが彼の基本だからである。
「魚には、食べ時があります。獲れたてから、刺身にいい時分、握り、炙り、煮時、とね」
中澤氏はバブル期前後から始まった「刺身鮨」の隆盛を嘆く。鮨にいい頃合いを考えず、新鮮でありさえすればいいという通りいっぺんな考えが、いつしか本来の江戸前の仕事を駆逐してしまったからだ。
塩で、酢で、昆布で〆る。冷蔵庫で、氷温で、真空で寝かす。熟成の手法は様々なれど、すべては魚本来の個性をより引き出すため。だがどの手法を採り、何日寝かすかは、中澤氏とて慎重である。
「まぐろはどこでいかなる漁法で採れたものかが分からなければ、怖くて熟成させられません」
だからこそ魚の情報を握る卸との関係性が大切だと説く。鰹ならとれたてでは味が出ぬ、血合いに近いところは若いうちがいいが、腹は寝かせたい……。そんな風にひとつの魚でも時間軸と部位により下処理を変え、お客に供す。それはすべて、「旨い鮨」のために、他ならない。