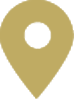彼女は日本人で、名前はユリカ。
僕は、財布のお礼にという口実で、バー『The Pawn』にユリカを誘った。
透き通るような白い肌に、柔らかな髪。黒い瞳をまばたきさせるたびに、長い睫毛が目元に影を落とす。おそらく20代後半くらいだろうか。
「ユリカさんは、こっちに住んでいるの?」
「ううん、東京に住んでいるの。今回は、旅行よ」
店内が少し騒がしいせいか、彼女は顔を寄せて耳元で話すので、僕の胸は終始高鳴っていた。
いつからか恋愛というものに一切興味をなくし、氷のように凍結していた僕の心。それが一気に溶け始めたような、そんな感覚だ。
それから何時間も話し続けた。彼女といるのは本当に楽しくて、店を出た後も「タクシーを拾おう」と言いながら、彼女とこのまま会えなくなるのは嫌だと思った。
その瞬間、ユリカがふらりとよろめいて、僕はとっさに彼女を抱き止める。
「大丈夫?」
彼女はその問いには答えず、僕の腕に身を委ねたまま、思いついたように言った。
「ねえ、偶然財布を拾って旅先で出会うなんて…映画か何かだったら、運命の出会いっていうのかしら」
僕の心臓がドクンと跳ね上がる。
僕たちはそのまま数秒間、互いに無言で見つめ合っていた。
—このままキスをしてしまおうか…。
ところが顔を近づけた途端、彼女はスッと身体を離した。
「なーんてね。運命の出会いなんて素敵な響きだけど、私にはあいにく、婚約者がいるの。
香港にはね、こっちに住んでいる婚約者に会いに来たの。といっても彼、仕事で忙しくて、こうして私は一人で時間を潰していたのよ…」
「そうだったんだ…」
彼女の薬指には、まばゆいほどに光り輝く、大きなダイヤモンドのエンゲージリングがあった。僕は呆然とその手元を見つめる。
—また、会えないかな?
彼女がタクシーに乗り込む直前、そう喉まで出掛かったが、口にする勇気はなかった。
ユリカが去った後も、彼女がつけていた香水の甘くスパイシーな香りが、僕のシャツに残って消えなかった。
翌日の夜、僕は、銅鑼湾(コーズウェイベイ)にある日本料理店『Ta-Ke』にやってきた。
僕が今回香港を訪れたのは、実はワインのメーカーズディナーに参加するためでもある。ニュージーランドのワイナリー「シャトー・ワイマラマ」が、銀座の鮨店『はっこく』とコラボして開催するイベントだ。
イベントの目玉とも言えるのが、「シャトー・ワイマラマ」の最高峰赤ワイン「SSS 2009」だ。
総生産量は1,768本という希少さで、決して気軽に飲むことが出来ない最上級クラスのワイン。それをオンリストしている『はっこく』がコラボし、香港という地を舞台に実施する、スペシャルなメーカーズディナーなのだ。
日頃から東京で『はっこく』を行きつけにしている僕は、特別に大将から声をかけてもらい、香港一人旅も兼ねて思い切って参加することにした。
到着して店内をぐるりと見回すと、香港のアッパー層や、日本の有名企業の社長など、錚々たる顔ぶれが揃っている。
『はっこく』の大将が握る極上の鮨とともに、ついに最高峰赤ワイン「SSS 2009」が振るまわれた。
グラスを鼻に近づけると、熟したブルーベリーやカシス、リコリスやブラックペッパーのスパイス香や、バニラの香りがした。滑らかな口当たりに感動し、口の中に広がる長い余韻も楽しむ。
僕はふと、ユリカのことを思い出した。
昨日彼女が去ったあとも残っていた、スパイシーで甘く濃密な香りや、色っぽくてエレガントな所作。
今目の前にあるワインが、ユリカのイメージとぴったり重なったのだ。
そのとき突然、隣に座っていた男性から声をかけられた。
「こんなに濃厚な味わいの赤ワインが鮨に合うなんて、驚きましたよね」
見るからに上質な身なりをしたその男性は、佐藤茂と名乗り、日本で大手企業の会長を務めているらしい。
「確かに…」
いつも僕が鮨に合わせるのは、大抵シャンパーニュか白ワインで、カベルネ・ソーヴィニヨン100%のような力強い赤ワインを選ぶことはない。
ところが意外にも、『はっこく』の赤酢の鮨と「SSS 2009」の相性は、ピッタリだったのだ。
佐藤茂氏は、僕に向かって言った。
「カベルネ・ソーヴィニヨンと赤酢の鮨がこんなに合うっていうのに、鮨には白ワイン、って決めつけてしまう人がたくさんいる。残念なことです。
…常識や決めつけにとらわれてしまうのって、損をすると思うんですよね」
佐藤氏の一言は印象的で、その後も僕の頭からしばらく離れなかった。
そして、ふと考えたのだ。
—ユリカに婚約者がいるから諦めなくちゃいけないなんて、決めつけるのはやめよう。
帰り道に僕は、昨日彼女から聞いた番号に電話をかけた。
「ユリカさん。もう一度だけ僕と、香港で会ってほしいんだ」