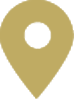◆
「あの日、既読になったのになかなか返信がなかったから…。何か失礼なことしちゃったかなって、気が気じゃなかったです」
西麻布にある『アズール エ マサ ウエキ』で、透君はそう言ってほほ笑んだ。普段すっきりした切れ長の目は、笑うと思いきり目尻が垂れて、その顔を見ると一気に緊張が解きほぐれる。
その日、私たちはたくさんのことを話しながら、ワインを楽しんだ。ワイン好きな私のために、本格的なペアリングが楽しめるお店を予約してくれたのだ。
一緒にいる時間が楽しければ楽しいほど、ある思いが頭によぎる。
―透君は、どんなつもりなのかしら。
仕事ができて、見た目もいい32歳の独身男。周りが放っておく訳はない。彼の同期の中尾君が、「透はズルいくらいにモテる」と言っているのを聞いたことがある。
しかも彼はとてもマメで、この食事までの数日の間だって、毎日連絡をくれたのだ。
透君に惹かれながらも、私は年上の女らしく慎重になっていた。穏やかな恋人との日常に刺激を与えてくれる年下の彼が、新鮮なだけかもしれない。これ以上、不用意に心を乱されたくなかった。
3時間ほどのコース料理はあっという間に終わりを迎え、そして帰り際。私はあることを目にしてしまった。
お会計を済ませ、透君が化粧室に席を立っている間、テーブルの上で彼の携帯が光った。思わずそのディスプレイに目をやると、そこには女性の名前が表示されていた。
―YURI―
胸が、どくんと波打つ。戻って来た透君は光る携帯をチラりと見て、そして…。それをそっと裏返した。
この間圭吾に気づかれないように私がしたのと、全く同じ動作。その光景を見て、私の心は鉛のように重くなった。
決して認めたくはないが、この感情は「嫉妬」以外、何者でもない。透君に惹かれているという事実を、受け入れざるを得なかった。
◆
週末、いつも通り圭吾の家に行くときには、もう心に決めていた。
―圭吾とは、別れよう。
これから透君と、どうなるかは分からなかった。35歳の独身女が、次の保証がないまま別れるなんて、愚かなことなのかもしれない。
しかしこれまでの経験から1つだけ、分かることがある。透君に惹かれながら圭吾と付き合えば、悪いところばかりに目がいき、私の中でたしかに存在していた彼への愛情さえ、根こそぎ奪ってしまうのだ。
「別れてほしいの」
私がそう言ったとき、圭吾は右眉を少しだけ上げた。
「…何を言ってるんだ?」
そして私はもう一度、言った。できるだけ感情を押し殺して、毅然と。
「別れてほしいの」
すると彼はこれまでに聞いたことのないような低い、そして呻くような声で言った。
「僕たちは、うまくいってるじゃないか」
その言葉に、私はもう、事実を打ち明けるしかなかった。
「違うの…。他に気になる人ができたの」
「気になってるだけで? それで僕と別れると言ってるのか…? 僕たちは充分、うまくいってるじゃないか」
話は平行線のまま、最終的には「もう一度、考え直してくれ」と言われ、圭吾の家を後にした。お互いの神経をすり減らす、とても長い話し合いだった。
そして、透君からの連絡はこの間の食事以降、すっかり途絶えていた。