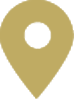「麻里ちゃん、突然だけど今夜空いてない?」
電話にでると、泉の透明感ある声が耳に飛び込んできた。
「実は、今夜彼と行こうと思って予約してたレストランがあるんだけど、彼が急に行けなくなってしまったの。麻里ちゃんの都合がよければ、どうかしら?」
思いがけない、急な誘いだった。
「本当ですか?!ぜひ、行きたいです」
高史に会うまで、特に何の予定もない。一人で家にいてもネガティブな想像が膨らむばかりだ。こんな時は、少しでも誰かと居たかった。
だから泉からの誘いは、まるで救いの手を差し伸べられたようにさえ思えた。
18時に会社を出て、向かったのは品川の『スーホルム』。
はじめこそ仕事の話をしていたものの、2杯目のワインを飲み始め、弱気な言葉をひとつ口にすると、もう止められなくなってしまった。
「もうすぐ30歳になるっていうのに、彼氏に振られるかもしれないんです。キャリアも、思い描いていた場所にはまだまだ遠いですし。私、こんなんで30歳になっていいのかなって、不安なんです」
お酒の力も借りて、最近のモヤモヤを正直に打ち明ける。
「へえ、麻里ちゃんってキャリアのことでも悩んでたの?」
「はい……。後輩ができて偉そうに教えたりしてますけど、本当は自信がない時もあって。30歳までにはチームリーダーになるんだ!なんて息巻いてたのに、そうなれるのはまだまだ先みたいだし」
目の前にいる泉は、美人で、仕事ができて、人当たりもよく、信頼できるパートナーに愛されている女性。
女が欲しがるものを、生まれながらに持っているような彼女に、こんな悩みを打ち明ける自分が惨めにさえ思えてきた。
泉のような女性を見る度に、世の中はなんて不公平なのだろうと思う。
今だって、ワイングラスを持ちあげるその動作ひとつも、女である自分も見惚れてしまうほど美しい。
「麻里ちゃんったら、20代の頃の私とまったく同じね」
ずっと話を聞いていた泉が、そう言っていきなりくすくす笑い始めた。
それも、自分とは似ても似つかない彼女が「まったく同じ」なんて言うのだ。
「私も20代の頃は、30歳までに達成したいことをリストアップしてたの。麻里ちゃんみたいにリーダーになるとか、結婚したいとか」
「え、結婚?」
思わず大きな声を出してしまった。